「オールロードバイク・レボリューション」著者ヤン・ハイネさんが来日。アメリカの自転車雑誌編集長でもある氏と日本の友人たち7人で房総のグラベルを走った。日米の自転車事情について氏と語り合いながら、美しい風景のなかペダルを進めた。グラベル&オールロードが流行している理由や今の状況、そして将来の展望をサドルの上で話し合ったカルチャートーク。
 ヤン・ハイネさんを迎えて房総グラベルを走った7人 photo:Naoshige Yoshimura
ヤン・ハイネさんを迎えて房総グラベルを走った7人 photo:Naoshige Yoshimura
アメリカは印刷文化の盛んな国だ。歴史を彩ってきた雑誌の多くがアメリカから生まれてきたし、大量印刷が隆盛を極めたあとには、ZINEのような私的で小規模な印刷メディアも登場した。自転車の雑誌も昨今の出版不況に翻弄されているとはいえ、今もたくさんある。
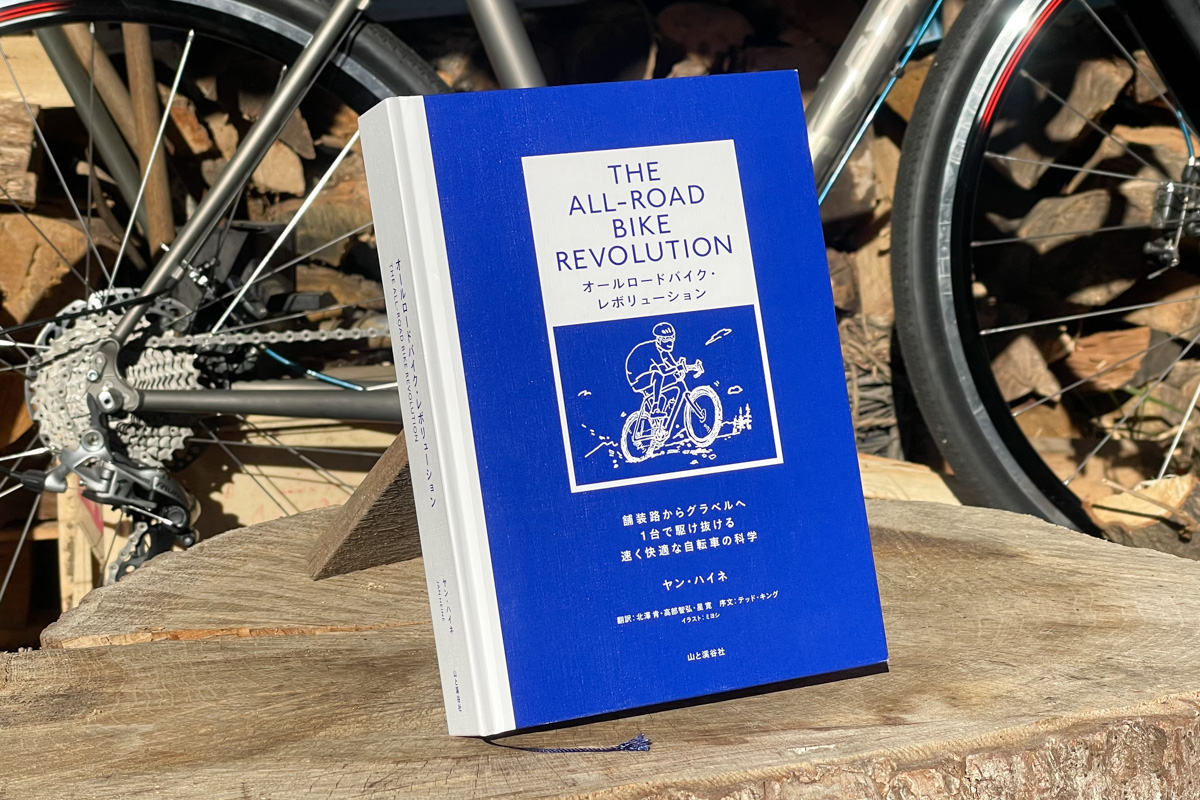 ヤン・ハイネ著「オールロードバイク・レボリューション」 (山と渓谷社) photo:Makoto AYANO
ヤン・ハイネ著「オールロードバイク・レボリューション」 (山と渓谷社) photo:Makoto AYANO ヤン・ハイネ氏が編集長をつとめる季刊誌 Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー) photo:Makoto AYANO
ヤン・ハイネ氏が編集長をつとめる季刊誌 Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー) photo:Makoto AYANO
そんなアメリカの自転車雑誌の中でも独特の立ち位置にあるのが「Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー)」(BQ)誌だろう。誌面を彩るのはツール・ド・フランスなどのトップレースではなく、パリ〜ブレスト〜パリなどの超長距離ブルベやUnbound Gravelなどのグラベルレース、1,000マイルレース「Arkansas High Country Race」などのビッグライドのドキュメント。そして他媒体では取り上げられることの少ないであろうニッチなパーツのインプレッションである。なかでもバイクテストはときに1台で600kmのグラベルやロングライドを乗り込むなど、走ることに徹底しているのがユニーク。
「グラベル主体のロングライドや、それにまつわるオールロードバイクについての雑誌」というのが一番平易な説明になるかもしれない。
 Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー)編集長、ヤン・ハイネさん photo:Naoshige Yoshimura
Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー)編集長、ヤン・ハイネさん photo:Naoshige Yoshimura
そんなBQ誌で編集長を務めるのが、ヤン・ハイネ氏。誌面での製品インプレッションや紀行記事には主筆として登場することも多い。そんな「走って・撮って・書く」編集長が来日するタイミングで、シクロワイアードの綾野真編集長からライドのお誘いがあった。
綾野さんが書いたツール・ド・フランスの取材記事などを読み、その独自の視点やジャーナリズム、自転車や走ることに対するパッションを感じたヤンさんが「面会したい」と綾野さんにコンタクトしたところ、綾野さんは「せっかくだから一緒にライドしましょう」と誘ったとのこと。綾野さんもまた「走って・撮って・書く」人であり、ふたりはどこか通じるところを感じていたのかもしれない。
房総でのグラベルライドが決まると、砂利道を走りたい自転車業界関係者が自然と集まった。ちょうどヤンさんの著書「オールロードバイク・レボリューション」の日本語版(綾野編集長によるブックレビューはこちら)が刊行されたタイミングであり、この本の中で語られた哲学を、本人と一緒に実地で共有できるまたとない機会となったのであった。
 冬の房総は水仙の花の最盛期を迎えて甘い香りが広がる photo:Makoto AYANO
冬の房総は水仙の花の最盛期を迎えて甘い香りが広がる photo:Makoto AYANO
年の瀬迫る12月の末日、日差しのまばゆい南房総には水仙の花が最盛期を迎えて咲き、春の気配さえただよっていた。照葉樹の雑木林に囲まれたマイナー林道を選んで、標高の高い山がない南房総の低山域を縫うように走った。かつて海の底だった土地が隆起してできた房総の地形は変化に富み、古代から人の手によって造られた素掘りトンネルがあちこちにあり、ときに崩落や通行止めによって途絶える道をたどりながら、7人は語り合いながら日暮れまで走った。
 初見のグラベルに嬉々として走るヤン・ハイネさん photo:Makoto AYANO
初見のグラベルに嬉々として走るヤン・ハイネさん photo:Makoto AYANO
コロナ禍以前の2019年ぶりの来日というヤンさんは、日本を愛し、機会あるごとに日本各地を自転車で走ったという。大弛峠、しらびそ峠といったワードが次から次へと出てくる。また、自らの走りに必要なパーツを日本のメーカーと協働して開発し、自社製品として製品化している。そのため産業界からの日本の自転車文化への造詣も深い。
 浦賀水道の先には三浦半島がすぐ近くに臨めた photo:Makoto AYANO
浦賀水道の先には三浦半島がすぐ近くに臨めた photo:Makoto AYANO
 グラベルを往くヤンさん。グラベルイベントの最高峰であるアンバウンドグラベルXLクラスを完走する健脚の持ち主でもある photo:Makoto AYANO
グラベルを往くヤンさん。グラベルイベントの最高峰であるアンバウンドグラベルXLクラスを完走する健脚の持ち主でもある photo:Makoto AYANO
房総でのライドは初めてだったヤンさん。「私は山岳サイクリングが好きで、日本が好き。房総グラベルは冒険的で本当に楽しかった。急峻な丘があちこちにあったし、走ったルートは本当に美しかった。海の眺めと森に囲まれた丘陵。浜辺の古い家並みを抜けて、大昔に人が手で掘ったトンネルをいくつもくぐった。人ひとりがやっと通れる穴を抜けた先に現れた美しい神社を参拝し、道中の安全を祈願した。そして道の魅力。曲がりくねった舗装路はやがてグラベルへと変わる。またはその中間の状態、かつては舗装されていた道が傷み、グラベルに戻ったようだった。ツイスト&ターンを繰り返す細路のダウンヒルを下るのは本当に楽しかった」と、このライドを心から愉しんでくれたようだ。
 南房総の林道に多くある素掘りトンネルを行く。ミステリアスな体験だ photo:Makoto AYANO
南房総の林道に多くある素掘りトンネルを行く。ミステリアスな体験だ photo:Makoto AYANO
 保田見林道にて。クルマ一台ギリギリ通れるほどの小道だった photo:Makoto AYANO
保田見林道にて。クルマ一台ギリギリ通れるほどの小道だった photo:Makoto AYANO
ライドを通じながら、またその夜に温泉に浸かり、民宿で海鮮料理をいただきながら氏と語らったことをここに記していこう。
お茶目さとダイナミックなライドスタイル
 「房総はグラベルフィールドとしてのポテンシャルを秘めている」ヤンさんに笑顔が覗く photo:Yufta Omata
「房総はグラベルフィールドとしてのポテンシャルを秘めている」ヤンさんに笑顔が覗く photo:Yufta Omata
「オールロードバイク・レボリューション」の日本語版には、ところどころ断定的な表記がなされており(しかし日本的な不断の文体に慣れているとそれが心地よい)、そもそもこの本が、サイクリストが一般に抱いて疑わない常識を一部切り崩そうとするのものだから、語調の強さが印象に残る。……がために本人もまた、「堅物」なのかもしれないと身構えていたら拍子抜け。とても柔和で、よく冗談を言っては舌を出す茶目っ気たっぷりの人物であった。
 アメリカでは身近にグラベルが多いという。日本ではエリアを選ばないといいグラベルが無いのが実情でもある photo:Yufta Omata
アメリカでは身近にグラベルが多いという。日本ではエリアを選ばないといいグラベルが無いのが実情でもある photo:Yufta Omata
およそ90kmに、獲得標高2,000m強というコースプロファイル。行程の3割ほどはグラベルを走るルートで、房総らしく細かな急坂のアップダウンを繰り返す。おそらくはタフな部類に入るこのライドで、最も快活でエネルギッシュに走るのがヤンさんなのであった。
来日に際して愛車を持ってこれなかったヤンさんは、Vaast bikeジャパンの厚意で借り受けたグラベルバイクで縦横無尽に走った。登坂が始まれば、ペースを上げて先行する「フォトアタック」を見せる。集団の先で待ち受けてカメラを構えるのだ。グラベルの下り坂では、荒れた路面も涼しい顔で突っ込んでいく。「走って・撮って・書く」編集長の面目躍如といったところだろうか。
 トンネルを抜けた先の岩盤には神社があった photo:Makoto AYANO
トンネルを抜けた先の岩盤には神社があった photo:Makoto AYANO
初対面だったのに、走ることで仲を深めた7人。ヤンさんは新しいライド仲間たちと知り合えたことを喜んでくれたようだ。
「一緒に走った仲間たち、彼らは日本の自転車界では有名なメンバーで、皆すごいサイクリストたちだった。上りでは速く、下りはそれ以上だった。どう走ってもお互いの動きが分かる。まるで長い知り合いか、すっかり信頼しきった友人同士のように感じた。気が楽だったし安全だった。崩落で道が塞がれていたときでも、皆がそれは大した問題じゃないと分かっていた。僕らはただ乗り越えてライドを続けた。小さな冒険はいい思い出になった。急峻な丘を上り下りする間、ずっと興味深いお喋りを愉しんだ。外でバイクに乗る完璧な一日だった。素晴らしい房総のグラベルルートを案内してくれてありがとう」。
この日のライドの模様は、いずれBicycle Quarterly誌の記事にする予定だという。
 祈りを捧げるヤンさん。神社での作法も慣れたものだ photo:Makoto AYANO
祈りを捧げるヤンさん。神社での作法も慣れたものだ photo:Makoto AYANO
 エピックライドの終わりに温泉民宿で乾杯 photo:Makoto AYANO
エピックライドの終わりに温泉民宿で乾杯 photo:Makoto AYANO 安房勝山の民宿で供された舟盛りをいただく photo:Makoto AYANO
安房勝山の民宿で供された舟盛りをいただく photo:Makoto AYANO
ライドの様子は写真でお見せするとして、走りながら、民宿で旬の伊勢海老の刺し身をいただきながらヤンさんと語り合ったなかで印象に残った話を綴りたい。
ヤンさんがBQ誌を創刊したのは2002年。当初はほとんどリトルプレスのような小規模な自転車雑誌だった。氏は気候変動についての博士号を持つ科学者であり、その実証的な姿勢が書き手としてのベースにある。徹底した実地テストを行うBQ誌のインプレ記事は、次第にファンを獲得し、雑誌の規模も大きくなっていった。サイクリングブランドのマニュアル翻訳などを仕事で手掛けていたこともあり、機材に関する豊富な知見は多いにBQ誌に活かされてきた。
共に一日を走って、何よりも印象的だったのは氏のライドのダイナミックさだ。かつては競技者を目指したそのフィジカルもさることながら、急坂の登坂に一言も弱音を吐かず、ぐいぐいと力強く走っていく。まさに「オールロードバイク・レボリューション」で表現されているスポーツとしてのサイクリングを体現する走りで、ここで氏の著作とキャラクターとが一致したのだった。
 ヤン・ハイネ氏はつねに同誌のプロダクツテスターであり、紀行文を寄せるライダーであり、編集長である
ヤン・ハイネ氏はつねに同誌のプロダクツテスターであり、紀行文を寄せるライダーであり、編集長である
なぜオールロードバイクか
ーー著作を拝読して、狭い意味でのロードバイクではなく、一台でグラベルから舗装路までを走れる「オールロードバイク」への情熱とそれがもたらすサイクリングの可能性を感じました。ヤンさんがオールロードバイクに夢中なのはなぜなのでしょうか?
JH 「本の第1章にも書いたけれど、オールロードバイクならどんなところでも走れるからだよ。舗装路ではロードバイクに劣らないフィーリング、それでいで砂利道も走れるし、ロングディスタンスも、あるいはキャンプツーリングだってできてしまう。そしてなにより、そうやって色んな走り方をすることが純粋に楽しいからだよ。
ロードバイクのデザインは成熟しているから、新しいパーツやフレームはどんどん出てきても、ジオメトリやどんなタイヤを採用するかといった、バイクのゴールというか、方向性はどのメーカーも似ているよね。メーカーの造るグラベルバイクやオールロードバイクは、ジオメトリひとつをとっても、実はロードレーサー的な乗り味を目指したものもあれば、MTB的な乗り味のものもあったりする。パッと見ただけだとドロップハンドルに太いタイヤだから似ているように見えるけれど、乗ってみるとメーカーによって全く乗り味が異なったりする。そもそも、クルマが走れるようなグラベルなのか、シングルトラックに近いテクニカルなグラベルかで、ベストなライディングポジションなんかも変わってくるしね。今まさに何が正解なのか、自転車業界も手探りで見極めようとしている段階なんだ。
バイシクルクオータリー誌のチームでは、グラベルだらけのフィールドへよく走りに出かけていたから、路面状況を問わずにどこでも走ることができる「オールロードバイク」の可能性をかなり早くから探っていたと思う。具体的に言うと、ありとあらゆる検証を行って、オールロードバイクに必要な性能は何かをリサーチしたんだよ。その20年にわたるリサーチの結果を「オールロードバイク・レボリューション」にまとめたんだ。
最近では、グラベルバイクのテクノロジーがロードバイクに取り入れられることも増えたよね。例えば、今ではロードレーサーも28mmぐらいのタイヤを使うようになったし、ディスクブレーキも一般的になってきた。友人のジェラルド・ブルーメン(Cerveloの創始者)も「もうすぐワンバイのロードバイクも増えてくるんじゃないかな」なんて言っていたよ。これから、どんな風にバイクが進化していくのか楽しみだよね。
ーー副題に「速く快適な自転車の科学」とある通り、この本に通底する科学的で実証的な文章を興味深く読みました。今、日本ではグラント・ピーターセンの「ジャスト・ライド」が自転車の実践書として翻訳が出ていますが、この本との大きな違いはこの態度かと思います。いかにヤンさんは書き手・編集者としてこうした視点を形成されたのでしょうか。
JH 「私のオリジンはドイツにあって、若い頃は自転車ブランドのマニュアルの翻訳を仕事にしていたんだ。サイクリングプロダクトにまつわる知識を蓄えるとともに、科学者としての気質が実証的な視点をもたらしたのだと思う。
それに、サイクリストとして経験を積んで多様な走りを楽しむようになるほどに、今まで常識とされてきたことに対しても「本当にそうなのか? 真実なのか?」と疑問が生まれてきたんだ。そうなると、調べずにはいられない。だから、大学の風洞実験の研究施設を借りて空気抵抗の試験もおこなったし、実際に走って検証もした。自転車のユニークなところは、動力が人力であること。だからラボでの実験だけじゃダメで、例えば、自転車の振動が人の身体に与える影響まで検討していかなくちゃいけない。そういう視点でリサーチしたのは、かなり新しいんじゃないかな。
グラント・ピーターセンと私の違いは、科学的であるかというよりもレースに対する姿勢の違いかもしれないね。彼はアンレーサー(レースをしない人)でありたいと説く。私はのんびりと峠超えをして温泉宿でまったりするような情緒的なサイクリングも好きだけれど、同時にレースも好きなんだ。プロレースの行きすぎた側面には同意しかねる点もあるけれど、速く走ることの喜びやレースを走る中での発見は確実にあって、レースが自転車を進化させてきたことは否定できないからね」。
 ヤン・ハイネ氏。今回はVaast Bikesジャパンの厚意により借り受けたグラベルバイク A/1で走る photo:Makoto AYANO
ヤン・ハイネ氏。今回はVaast Bikesジャパンの厚意により借り受けたグラベルバイク A/1で走る photo:Makoto AYANO
「グラベル」の射程距離
ーーいま、日本のサイクリングシーンはグラベルを自分たちの文化にしようと消化している段階だと感じています。どうしてもアメリカのようなフィールドとは違うので、そのまま取り入れられません。そこが面白く、また掴みどころがないと実感しています。
JH 「山がちな日本のグラベルはどうしても急な上り下りや、荒れた路面が多くなることは私も感じている。アメリカだと行政に予算がなくて舗装ができないという理由から未舗装路・グラベルがたくさんあり、それがライドフィールドになっているという側面がある。日本はどんな田舎でもほとんど舗装されていて、来る度にすごい国だと思わされるよ(笑)。とはいえ、ロードレーサーでは峠(山道)の下りでは荒れた舗装路やグレーチングに気を使ってスローダウンする、なんてことも多いんじゃないかな。そんな時、太いタイヤを履いたグラベルバイクなら、より快適で安定した走りができる。
同時に、日本の自転車文化がいかに独自の美学と楽しみ方を追求してきたかについても感嘆する。フレームビルダーたちの優れた技術と経験から生み出される機能的で高性能なバイク造りから、パスハンティングの流行までオリジナルな自転車の楽しみが息づいている国だから、グラベルもどういう解釈がされていくのか楽しみだね。今日のライドでは、その一端を見た気がするよ」。
 林道の行く手に崩落が有り、担ぎ上げを強いられた photo:Makoto AYANO
林道の行く手に崩落が有り、担ぎ上げを強いられた photo:Makoto AYANO
ーーヤンさん自身がアンバウンドグラベルのXLクラス(560km)を走るライダーでもありますが、アメリカのグラベルシーンの盛り上がりの理由は何か考えられますか?
JH 「アメリカではしばらくシクロクロスの人気が非常に高かった。大規模な大会では、普段は自転車に乗らないような一般人も会場に観戦に来ていたりして、単なる自転車イベントを超えるお祭りのような人気ぶりだったんだ。ただ、ここ数年、シクロクロスに夢中だった人がグラベルライドに移行している傾向がある。ロードバイク的にも乗ることが出来る”オールロード・グラベルバイク”が登場してきたこと、また移動と旅の要素が入るグラベルライドに人々が惹かれているんだろうね。シクロクロス会場に来る人は減ってきているけど、それでも昔はシアトルのレースで各カテゴリー15人もいないような時代もあったんだから、長い目で見ればシクロクロスもアメリカで定着しているということはできるだろうね」。
 自転車の話で夜が更けていく。話題はヤンさんのルネ・エルスのスペックやグラベルライドについて photo:Makoto AYANO
自転車の話で夜が更けていく。話題はヤンさんのルネ・エルスのスペックやグラベルライドについて photo:Makoto AYANO
日本には走って楽しい舗装の山道がたくさんあるけれど、アメリカでは通常、そうした道はグラベルなんだ。だからロードバイクで走ろうと思うと交通量の多い道がメインになる。これまではそれが普通だった。私がグラベルに魅力を見出して、グラベルバイクやタイヤを作り始めた2000年代の前半は、まだグラベルライドはニッチなスポーツだった。
グラベルが脚光を浴び始めたのは、テッド・キング(元UCIプロツアーのレーサー)の影響が大きいと思う。2016年にテッドがUnbound Gravelで勝利して、その頃からロードレーサーたちがグラベルの面白さに気がつき始めたんだ。興味深いことに、この時にロードレーサー達だけじゃなくて、これまで自転車ツーリングを楽しんでいた人やMTB乗りまでもがグラベルに関心を持ったんだ。
グラベルレースにはロードレースとは少し異なる「自由な感じ」がある。どちらが良いとか悪いじゃなくてね。例えば、前回のUnbound Gravelではサガンと並んでスタートできて話題になったよね。それってロードレースではちょっと考えられない。女性ライダーの活躍も目覚ましいよ。アメリカのグラベルレースは、性別を問わずスタート地点に立ち、同じコースを走る。これって、ロードレースではあまりなかったことなんだ。
チームで走るロードレースは勝敗が重要だけれど、グラベルレースの場合、ライダーがそれぞれに目標を決めて、そのゴールに向かって走ればいい雰囲気がある。だから、トップライダーのタイムから数時間遅れてフィニッシュしたって、全く問題ない。フィニッシュでは観客皆がフィニッシャーの走りを讃えるし、誰もが主役になれる。そんなところもグラベルレースの魅力じゃないかな。

アンバウンド・グラベルを走ったヤン・ハイネ氏(右)。駆るのは自らプロデュースするルネ・エルス製品を搭載したカスタムフレームのオールロードバイクに極太タイヤの組み合わせ ©Jan Heine
日本のレースで言ったら、ライダーが思い思いのスタイルやバイク、機材で楽しんでいる感じが、2016年に走ったMTBレース、セルフディスカバリーアドベンチャーin王滝に少し似ているかもしれない。ちなみにSDA王滝はスムースなグラベルだと思って、組んだばかりのオールロードバイクで走ったんだよ。ロードバイクに近い乗り味のね。でも、どちらかといえばMTBのコースだった。日本の皆さんはご存知だと思うけど、ハードなアップダウンが連続するガレたグラベルだったから、ダウンヒルもぜんぜん休めなかった(笑)。バイクの個性があまり活かせなかったから、次はもうちょっとMTBよりのオールロードバイクを考えるよ。今はグラベルクラスもあるみたいだしね。こんな風に、グラベルレースはどんなバイク、装備で走るかを考えるのも楽しみの一つ。野辺山グラベルチャレンジはまだ走ったことがないけれど、面白そうだね。いつか走る機会があれば良いなと思っているよ。
日本のグラベルはアメリカのグラベルと比べると、少しテクニカルかもしれない。今回の房総ライドもそうだったけれど、どちらかといえば幅員の狭いガレたグラベルが多い印象。アメリカのグラベルは比較的スムースだし、クルマが余裕で走れる幅員のグラベルも少なくない。もちろんかなりガレたグラベルやシングルトラック、テクニカルなパートもあるけれど、そこがメインではない感じなんだ。オールロードバイクやグラベルバイクなら、ロードバイク感覚の延長線上で走れる道もたくさんある。だから、より多くのサイクリストがグラベルに移行しやすいのかもしれないね。
と、いろいろ話したけれど、なんと言っても、グラベルライドは楽しい! それがグラベルシーンを盛り上げている理由だと思う」。
何よりも、ストーリーが大事
ーー「バイシクルクォータリー」誌は創刊20年を迎えたとのことですが、自転車雑誌の編集をする上で大切にしていることは何でしょうか。
JH 「なによりもまず、ストーリーが大事なんだ。読者を引き込み、そのライドを自分が走っているかのように感じるようなストーリーを語ることが雑誌の役割だと思っている。そのうえで、徹底的な機材テストの記事が読めることもBQの特徴になっているのではないかな。
バイクをテストするときは走行レポートを重視しているよ。1台のバイクをテストするために最低でも300kmは走る。夜通し走るようなビッグライドに出かけることもあるし、新たなルートの開拓に出掛けることもある。ルートは毎回、テストするバイクのポテンシャルを見極めながら決めるんだ。バイクの特性にあった、それでいてちょっと攻めたルートを走ってみて初めて見えてくるバイクの個性もあるからね。そうしたバイクのテストのリポートにはドラマがあるから、読み物としても面白いんだ。
面白いことに、BQはアメリカで唯一、グロサリーストア(食料品店)で販売している自転車雑誌なんだ。しかも結構売上がいいんだよ。オーガニックフードの隣に自転車雑誌があるなんて素敵だろう?(笑) おそらくは健康志向の人たちに自転車の引き合いがあるということなのだろうが、ストーリーとして読ませる記事があるからこそ、彼らに手に取ってもらえているんだろう」。
BQ誌や書籍を刊行していくモチベーション、その情熱はどこにあるのでしょうか?
JH 「とにかく自転車に乗ることが好きで、その喜びを分かち合いたいということ。だから、『とにかく、乗ろう』という言葉に尽きるね。自転車に乗るときの楽しさ。情熱はそこから生まれてくるんだ」。
 尾根道のグラベルを行くと荒涼とした平原に出た photo:Makoto AYANO
尾根道のグラベルを行くと荒涼とした平原に出た photo:Makoto AYANO
〜 エピローグ 〜
「オールロードバイク・レボリューション」は、自転車初心者向けの本ではないと思う。これは、自転車に乗る楽しみを覚えながら、さらにその喜びを深めたい人、既存の自転車メディアの紋切り型の発信に食傷気味な人、あるいは自転車の魅力を自由であることと考えられる人のための本ではないか。そして一面では、そうした人は自転車乗りとして成熟していると言えるかもしれない。
「ホイールのエアロダイナミクスよりもライディングフォームを正す方が空力は良く速く走れる」と著書の中で諭すように、ちょっとした下り坂をヤンさんはコンパクトなフォームで走っていく。共に走り、語った一日を終えたいま改めて本を開くと、まさに彼の口調がそこには再現されているのだった。断定的ではあるけれど、そこかしこにチャーミングな言い回し。彼の20年に及ぶ編集人としての集大成と、サイクリストとしての成熟がこの本に結実している。(小俣雄風太)
ヤン・ハイネ|Jan Heine プロフィール
アメリカ・ワシントン州シアトルに本拠を置く、自転車タイヤ/パーツのブランド『René HERSE』(ルネ・エルス)を主宰。自転車雑誌『Bicycle Quarterly』編集長。大学在学中に自転車レースを始め、大学院博士課程修了のころにはツール・ド・フランスを目指すプロ選手と伍するライダーとなるが、興味は長距離アドベンチャーツーリングへ。2007年「パリ~ブレスト~パリ1200㎞」において北米からの参加者中、最速を記録(49時間59分)。2016年には、自社で開発した53mm×26インチ幅の超軽量ロードタイヤ(1本418g)を履いた、FIREFLY(※)で王滝100kmに参戦(6時間27分)。2021 年には「OREGON OUTBACK」(585 ㎞・獲得標高4,382 m、26時間13分)FKT。2022年「Unbound XL」(530km・獲得標高4713 m、25時間24分)、「Arkansas High Country Race」South Roop(784㎞・獲得標高9973 m、46時間59分)FKT。1990年代初頭から、カスケード山脈のグラベル(砂利道)ルートを踏査し、科学的知見とサイクリストの経験を基にタイヤとパーツを20年にわたり開発してきた。
※ FIREFLY(アメリカ東海岸のチタンを得意とするフレームビルダー。53mm幅のタイヤを使ったロードレーサーに近いジオメトリのバイクは、彼らにとっても初めての試みでチャレンジであった)
Bicycle Quarterly(年4回発行)
https://www.bikequarterly.com
Rene Herse Cycles
https://www.renehersecycles.com
text:Yufta Omata
photo:Makoto AYANO,Yufta Omata,Naoshige Yoshimura
 ヤン・ハイネさんを迎えて房総グラベルを走った7人 photo:Naoshige Yoshimura
ヤン・ハイネさんを迎えて房総グラベルを走った7人 photo:Naoshige Yoshimuraアメリカは印刷文化の盛んな国だ。歴史を彩ってきた雑誌の多くがアメリカから生まれてきたし、大量印刷が隆盛を極めたあとには、ZINEのような私的で小規模な印刷メディアも登場した。自転車の雑誌も昨今の出版不況に翻弄されているとはいえ、今もたくさんある。
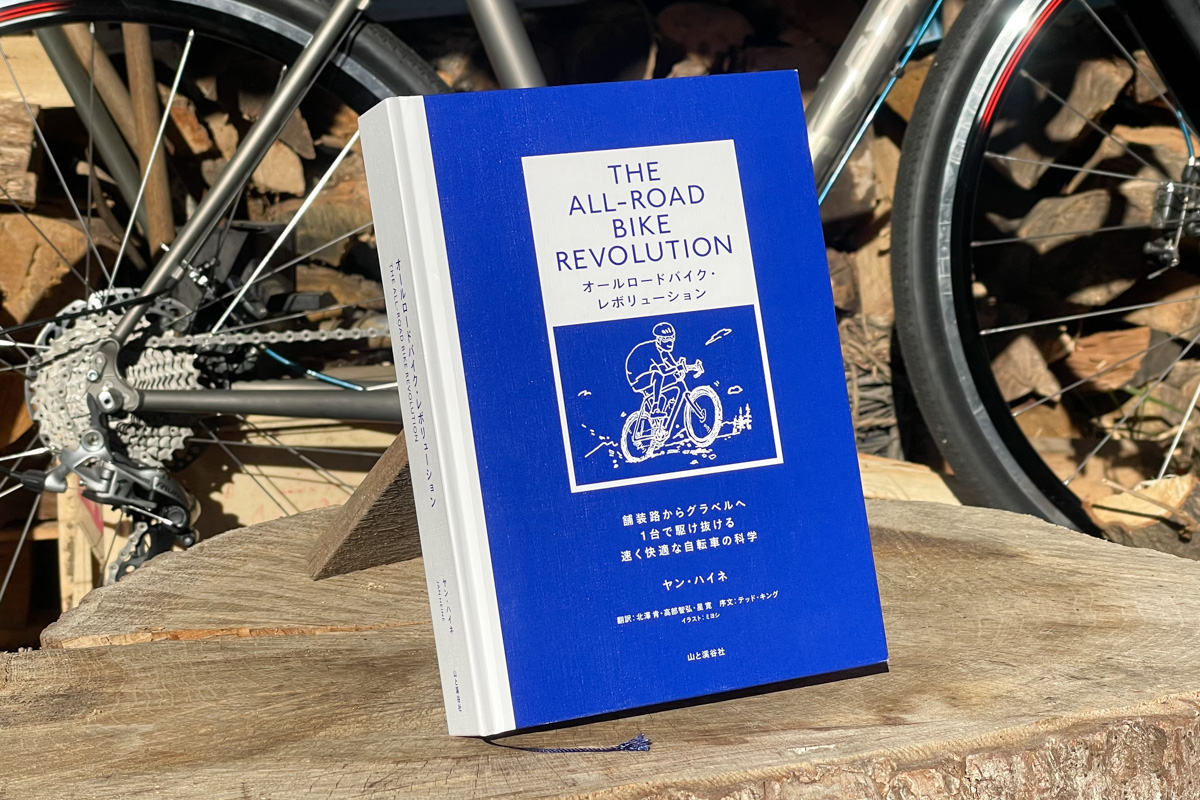 ヤン・ハイネ著「オールロードバイク・レボリューション」 (山と渓谷社) photo:Makoto AYANO
ヤン・ハイネ著「オールロードバイク・レボリューション」 (山と渓谷社) photo:Makoto AYANO ヤン・ハイネ氏が編集長をつとめる季刊誌 Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー) photo:Makoto AYANO
ヤン・ハイネ氏が編集長をつとめる季刊誌 Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー) photo:Makoto AYANOそんなアメリカの自転車雑誌の中でも独特の立ち位置にあるのが「Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー)」(BQ)誌だろう。誌面を彩るのはツール・ド・フランスなどのトップレースではなく、パリ〜ブレスト〜パリなどの超長距離ブルベやUnbound Gravelなどのグラベルレース、1,000マイルレース「Arkansas High Country Race」などのビッグライドのドキュメント。そして他媒体では取り上げられることの少ないであろうニッチなパーツのインプレッションである。なかでもバイクテストはときに1台で600kmのグラベルやロングライドを乗り込むなど、走ることに徹底しているのがユニーク。
「グラベル主体のロングライドや、それにまつわるオールロードバイクについての雑誌」というのが一番平易な説明になるかもしれない。
 Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー)編集長、ヤン・ハイネさん photo:Naoshige Yoshimura
Bicycle Quarterly(バイシクル・クォータリー)編集長、ヤン・ハイネさん photo:Naoshige YoshimuraそんなBQ誌で編集長を務めるのが、ヤン・ハイネ氏。誌面での製品インプレッションや紀行記事には主筆として登場することも多い。そんな「走って・撮って・書く」編集長が来日するタイミングで、シクロワイアードの綾野真編集長からライドのお誘いがあった。
綾野さんが書いたツール・ド・フランスの取材記事などを読み、その独自の視点やジャーナリズム、自転車や走ることに対するパッションを感じたヤンさんが「面会したい」と綾野さんにコンタクトしたところ、綾野さんは「せっかくだから一緒にライドしましょう」と誘ったとのこと。綾野さんもまた「走って・撮って・書く」人であり、ふたりはどこか通じるところを感じていたのかもしれない。
房総でのグラベルライドが決まると、砂利道を走りたい自転車業界関係者が自然と集まった。ちょうどヤンさんの著書「オールロードバイク・レボリューション」の日本語版(綾野編集長によるブックレビューはこちら)が刊行されたタイミングであり、この本の中で語られた哲学を、本人と一緒に実地で共有できるまたとない機会となったのであった。
 冬の房総は水仙の花の最盛期を迎えて甘い香りが広がる photo:Makoto AYANO
冬の房総は水仙の花の最盛期を迎えて甘い香りが広がる photo:Makoto AYANO年の瀬迫る12月の末日、日差しのまばゆい南房総には水仙の花が最盛期を迎えて咲き、春の気配さえただよっていた。照葉樹の雑木林に囲まれたマイナー林道を選んで、標高の高い山がない南房総の低山域を縫うように走った。かつて海の底だった土地が隆起してできた房総の地形は変化に富み、古代から人の手によって造られた素掘りトンネルがあちこちにあり、ときに崩落や通行止めによって途絶える道をたどりながら、7人は語り合いながら日暮れまで走った。
 初見のグラベルに嬉々として走るヤン・ハイネさん photo:Makoto AYANO
初見のグラベルに嬉々として走るヤン・ハイネさん photo:Makoto AYANOコロナ禍以前の2019年ぶりの来日というヤンさんは、日本を愛し、機会あるごとに日本各地を自転車で走ったという。大弛峠、しらびそ峠といったワードが次から次へと出てくる。また、自らの走りに必要なパーツを日本のメーカーと協働して開発し、自社製品として製品化している。そのため産業界からの日本の自転車文化への造詣も深い。
 浦賀水道の先には三浦半島がすぐ近くに臨めた photo:Makoto AYANO
浦賀水道の先には三浦半島がすぐ近くに臨めた photo:Makoto AYANO グラベルを往くヤンさん。グラベルイベントの最高峰であるアンバウンドグラベルXLクラスを完走する健脚の持ち主でもある photo:Makoto AYANO
グラベルを往くヤンさん。グラベルイベントの最高峰であるアンバウンドグラベルXLクラスを完走する健脚の持ち主でもある photo:Makoto AYANO房総でのライドは初めてだったヤンさん。「私は山岳サイクリングが好きで、日本が好き。房総グラベルは冒険的で本当に楽しかった。急峻な丘があちこちにあったし、走ったルートは本当に美しかった。海の眺めと森に囲まれた丘陵。浜辺の古い家並みを抜けて、大昔に人が手で掘ったトンネルをいくつもくぐった。人ひとりがやっと通れる穴を抜けた先に現れた美しい神社を参拝し、道中の安全を祈願した。そして道の魅力。曲がりくねった舗装路はやがてグラベルへと変わる。またはその中間の状態、かつては舗装されていた道が傷み、グラベルに戻ったようだった。ツイスト&ターンを繰り返す細路のダウンヒルを下るのは本当に楽しかった」と、このライドを心から愉しんでくれたようだ。
 南房総の林道に多くある素掘りトンネルを行く。ミステリアスな体験だ photo:Makoto AYANO
南房総の林道に多くある素掘りトンネルを行く。ミステリアスな体験だ photo:Makoto AYANO 保田見林道にて。クルマ一台ギリギリ通れるほどの小道だった photo:Makoto AYANO
保田見林道にて。クルマ一台ギリギリ通れるほどの小道だった photo:Makoto AYANOライドを通じながら、またその夜に温泉に浸かり、民宿で海鮮料理をいただきながら氏と語らったことをここに記していこう。
お茶目さとダイナミックなライドスタイル
 「房総はグラベルフィールドとしてのポテンシャルを秘めている」ヤンさんに笑顔が覗く photo:Yufta Omata
「房総はグラベルフィールドとしてのポテンシャルを秘めている」ヤンさんに笑顔が覗く photo:Yufta Omata「オールロードバイク・レボリューション」の日本語版には、ところどころ断定的な表記がなされており(しかし日本的な不断の文体に慣れているとそれが心地よい)、そもそもこの本が、サイクリストが一般に抱いて疑わない常識を一部切り崩そうとするのものだから、語調の強さが印象に残る。……がために本人もまた、「堅物」なのかもしれないと身構えていたら拍子抜け。とても柔和で、よく冗談を言っては舌を出す茶目っ気たっぷりの人物であった。
 アメリカでは身近にグラベルが多いという。日本ではエリアを選ばないといいグラベルが無いのが実情でもある photo:Yufta Omata
アメリカでは身近にグラベルが多いという。日本ではエリアを選ばないといいグラベルが無いのが実情でもある photo:Yufta Omataおよそ90kmに、獲得標高2,000m強というコースプロファイル。行程の3割ほどはグラベルを走るルートで、房総らしく細かな急坂のアップダウンを繰り返す。おそらくはタフな部類に入るこのライドで、最も快活でエネルギッシュに走るのがヤンさんなのであった。
来日に際して愛車を持ってこれなかったヤンさんは、Vaast bikeジャパンの厚意で借り受けたグラベルバイクで縦横無尽に走った。登坂が始まれば、ペースを上げて先行する「フォトアタック」を見せる。集団の先で待ち受けてカメラを構えるのだ。グラベルの下り坂では、荒れた路面も涼しい顔で突っ込んでいく。「走って・撮って・書く」編集長の面目躍如といったところだろうか。
 トンネルを抜けた先の岩盤には神社があった photo:Makoto AYANO
トンネルを抜けた先の岩盤には神社があった photo:Makoto AYANO初対面だったのに、走ることで仲を深めた7人。ヤンさんは新しいライド仲間たちと知り合えたことを喜んでくれたようだ。
「一緒に走った仲間たち、彼らは日本の自転車界では有名なメンバーで、皆すごいサイクリストたちだった。上りでは速く、下りはそれ以上だった。どう走ってもお互いの動きが分かる。まるで長い知り合いか、すっかり信頼しきった友人同士のように感じた。気が楽だったし安全だった。崩落で道が塞がれていたときでも、皆がそれは大した問題じゃないと分かっていた。僕らはただ乗り越えてライドを続けた。小さな冒険はいい思い出になった。急峻な丘を上り下りする間、ずっと興味深いお喋りを愉しんだ。外でバイクに乗る完璧な一日だった。素晴らしい房総のグラベルルートを案内してくれてありがとう」。
この日のライドの模様は、いずれBicycle Quarterly誌の記事にする予定だという。
 祈りを捧げるヤンさん。神社での作法も慣れたものだ photo:Makoto AYANO
祈りを捧げるヤンさん。神社での作法も慣れたものだ photo:Makoto AYANO エピックライドの終わりに温泉民宿で乾杯 photo:Makoto AYANO
エピックライドの終わりに温泉民宿で乾杯 photo:Makoto AYANO 安房勝山の民宿で供された舟盛りをいただく photo:Makoto AYANO
安房勝山の民宿で供された舟盛りをいただく photo:Makoto AYANOライドの様子は写真でお見せするとして、走りながら、民宿で旬の伊勢海老の刺し身をいただきながらヤンさんと語り合ったなかで印象に残った話を綴りたい。
ヤンさんがBQ誌を創刊したのは2002年。当初はほとんどリトルプレスのような小規模な自転車雑誌だった。氏は気候変動についての博士号を持つ科学者であり、その実証的な姿勢が書き手としてのベースにある。徹底した実地テストを行うBQ誌のインプレ記事は、次第にファンを獲得し、雑誌の規模も大きくなっていった。サイクリングブランドのマニュアル翻訳などを仕事で手掛けていたこともあり、機材に関する豊富な知見は多いにBQ誌に活かされてきた。
共に一日を走って、何よりも印象的だったのは氏のライドのダイナミックさだ。かつては競技者を目指したそのフィジカルもさることながら、急坂の登坂に一言も弱音を吐かず、ぐいぐいと力強く走っていく。まさに「オールロードバイク・レボリューション」で表現されているスポーツとしてのサイクリングを体現する走りで、ここで氏の著作とキャラクターとが一致したのだった。
 ヤン・ハイネ氏はつねに同誌のプロダクツテスターであり、紀行文を寄せるライダーであり、編集長である
ヤン・ハイネ氏はつねに同誌のプロダクツテスターであり、紀行文を寄せるライダーであり、編集長である なぜオールロードバイクか
ーー著作を拝読して、狭い意味でのロードバイクではなく、一台でグラベルから舗装路までを走れる「オールロードバイク」への情熱とそれがもたらすサイクリングの可能性を感じました。ヤンさんがオールロードバイクに夢中なのはなぜなのでしょうか?
JH 「本の第1章にも書いたけれど、オールロードバイクならどんなところでも走れるからだよ。舗装路ではロードバイクに劣らないフィーリング、それでいで砂利道も走れるし、ロングディスタンスも、あるいはキャンプツーリングだってできてしまう。そしてなにより、そうやって色んな走り方をすることが純粋に楽しいからだよ。
ロードバイクのデザインは成熟しているから、新しいパーツやフレームはどんどん出てきても、ジオメトリやどんなタイヤを採用するかといった、バイクのゴールというか、方向性はどのメーカーも似ているよね。メーカーの造るグラベルバイクやオールロードバイクは、ジオメトリひとつをとっても、実はロードレーサー的な乗り味を目指したものもあれば、MTB的な乗り味のものもあったりする。パッと見ただけだとドロップハンドルに太いタイヤだから似ているように見えるけれど、乗ってみるとメーカーによって全く乗り味が異なったりする。そもそも、クルマが走れるようなグラベルなのか、シングルトラックに近いテクニカルなグラベルかで、ベストなライディングポジションなんかも変わってくるしね。今まさに何が正解なのか、自転車業界も手探りで見極めようとしている段階なんだ。
バイシクルクオータリー誌のチームでは、グラベルだらけのフィールドへよく走りに出かけていたから、路面状況を問わずにどこでも走ることができる「オールロードバイク」の可能性をかなり早くから探っていたと思う。具体的に言うと、ありとあらゆる検証を行って、オールロードバイクに必要な性能は何かをリサーチしたんだよ。その20年にわたるリサーチの結果を「オールロードバイク・レボリューション」にまとめたんだ。
最近では、グラベルバイクのテクノロジーがロードバイクに取り入れられることも増えたよね。例えば、今ではロードレーサーも28mmぐらいのタイヤを使うようになったし、ディスクブレーキも一般的になってきた。友人のジェラルド・ブルーメン(Cerveloの創始者)も「もうすぐワンバイのロードバイクも増えてくるんじゃないかな」なんて言っていたよ。これから、どんな風にバイクが進化していくのか楽しみだよね。
ーー副題に「速く快適な自転車の科学」とある通り、この本に通底する科学的で実証的な文章を興味深く読みました。今、日本ではグラント・ピーターセンの「ジャスト・ライド」が自転車の実践書として翻訳が出ていますが、この本との大きな違いはこの態度かと思います。いかにヤンさんは書き手・編集者としてこうした視点を形成されたのでしょうか。
JH 「私のオリジンはドイツにあって、若い頃は自転車ブランドのマニュアルの翻訳を仕事にしていたんだ。サイクリングプロダクトにまつわる知識を蓄えるとともに、科学者としての気質が実証的な視点をもたらしたのだと思う。
それに、サイクリストとして経験を積んで多様な走りを楽しむようになるほどに、今まで常識とされてきたことに対しても「本当にそうなのか? 真実なのか?」と疑問が生まれてきたんだ。そうなると、調べずにはいられない。だから、大学の風洞実験の研究施設を借りて空気抵抗の試験もおこなったし、実際に走って検証もした。自転車のユニークなところは、動力が人力であること。だからラボでの実験だけじゃダメで、例えば、自転車の振動が人の身体に与える影響まで検討していかなくちゃいけない。そういう視点でリサーチしたのは、かなり新しいんじゃないかな。
グラント・ピーターセンと私の違いは、科学的であるかというよりもレースに対する姿勢の違いかもしれないね。彼はアンレーサー(レースをしない人)でありたいと説く。私はのんびりと峠超えをして温泉宿でまったりするような情緒的なサイクリングも好きだけれど、同時にレースも好きなんだ。プロレースの行きすぎた側面には同意しかねる点もあるけれど、速く走ることの喜びやレースを走る中での発見は確実にあって、レースが自転車を進化させてきたことは否定できないからね」。
 ヤン・ハイネ氏。今回はVaast Bikesジャパンの厚意により借り受けたグラベルバイク A/1で走る photo:Makoto AYANO
ヤン・ハイネ氏。今回はVaast Bikesジャパンの厚意により借り受けたグラベルバイク A/1で走る photo:Makoto AYANO「グラベル」の射程距離
ーーいま、日本のサイクリングシーンはグラベルを自分たちの文化にしようと消化している段階だと感じています。どうしてもアメリカのようなフィールドとは違うので、そのまま取り入れられません。そこが面白く、また掴みどころがないと実感しています。
JH 「山がちな日本のグラベルはどうしても急な上り下りや、荒れた路面が多くなることは私も感じている。アメリカだと行政に予算がなくて舗装ができないという理由から未舗装路・グラベルがたくさんあり、それがライドフィールドになっているという側面がある。日本はどんな田舎でもほとんど舗装されていて、来る度にすごい国だと思わされるよ(笑)。とはいえ、ロードレーサーでは峠(山道)の下りでは荒れた舗装路やグレーチングに気を使ってスローダウンする、なんてことも多いんじゃないかな。そんな時、太いタイヤを履いたグラベルバイクなら、より快適で安定した走りができる。
同時に、日本の自転車文化がいかに独自の美学と楽しみ方を追求してきたかについても感嘆する。フレームビルダーたちの優れた技術と経験から生み出される機能的で高性能なバイク造りから、パスハンティングの流行までオリジナルな自転車の楽しみが息づいている国だから、グラベルもどういう解釈がされていくのか楽しみだね。今日のライドでは、その一端を見た気がするよ」。
 林道の行く手に崩落が有り、担ぎ上げを強いられた photo:Makoto AYANO
林道の行く手に崩落が有り、担ぎ上げを強いられた photo:Makoto AYANOーーヤンさん自身がアンバウンドグラベルのXLクラス(560km)を走るライダーでもありますが、アメリカのグラベルシーンの盛り上がりの理由は何か考えられますか?
JH 「アメリカではしばらくシクロクロスの人気が非常に高かった。大規模な大会では、普段は自転車に乗らないような一般人も会場に観戦に来ていたりして、単なる自転車イベントを超えるお祭りのような人気ぶりだったんだ。ただ、ここ数年、シクロクロスに夢中だった人がグラベルライドに移行している傾向がある。ロードバイク的にも乗ることが出来る”オールロード・グラベルバイク”が登場してきたこと、また移動と旅の要素が入るグラベルライドに人々が惹かれているんだろうね。シクロクロス会場に来る人は減ってきているけど、それでも昔はシアトルのレースで各カテゴリー15人もいないような時代もあったんだから、長い目で見ればシクロクロスもアメリカで定着しているということはできるだろうね」。
 自転車の話で夜が更けていく。話題はヤンさんのルネ・エルスのスペックやグラベルライドについて photo:Makoto AYANO
自転車の話で夜が更けていく。話題はヤンさんのルネ・エルスのスペックやグラベルライドについて photo:Makoto AYANO日本には走って楽しい舗装の山道がたくさんあるけれど、アメリカでは通常、そうした道はグラベルなんだ。だからロードバイクで走ろうと思うと交通量の多い道がメインになる。これまではそれが普通だった。私がグラベルに魅力を見出して、グラベルバイクやタイヤを作り始めた2000年代の前半は、まだグラベルライドはニッチなスポーツだった。
グラベルが脚光を浴び始めたのは、テッド・キング(元UCIプロツアーのレーサー)の影響が大きいと思う。2016年にテッドがUnbound Gravelで勝利して、その頃からロードレーサーたちがグラベルの面白さに気がつき始めたんだ。興味深いことに、この時にロードレーサー達だけじゃなくて、これまで自転車ツーリングを楽しんでいた人やMTB乗りまでもがグラベルに関心を持ったんだ。
グラベルレースにはロードレースとは少し異なる「自由な感じ」がある。どちらが良いとか悪いじゃなくてね。例えば、前回のUnbound Gravelではサガンと並んでスタートできて話題になったよね。それってロードレースではちょっと考えられない。女性ライダーの活躍も目覚ましいよ。アメリカのグラベルレースは、性別を問わずスタート地点に立ち、同じコースを走る。これって、ロードレースではあまりなかったことなんだ。
チームで走るロードレースは勝敗が重要だけれど、グラベルレースの場合、ライダーがそれぞれに目標を決めて、そのゴールに向かって走ればいい雰囲気がある。だから、トップライダーのタイムから数時間遅れてフィニッシュしたって、全く問題ない。フィニッシュでは観客皆がフィニッシャーの走りを讃えるし、誰もが主役になれる。そんなところもグラベルレースの魅力じゃないかな。

日本のレースで言ったら、ライダーが思い思いのスタイルやバイク、機材で楽しんでいる感じが、2016年に走ったMTBレース、セルフディスカバリーアドベンチャーin王滝に少し似ているかもしれない。ちなみにSDA王滝はスムースなグラベルだと思って、組んだばかりのオールロードバイクで走ったんだよ。ロードバイクに近い乗り味のね。でも、どちらかといえばMTBのコースだった。日本の皆さんはご存知だと思うけど、ハードなアップダウンが連続するガレたグラベルだったから、ダウンヒルもぜんぜん休めなかった(笑)。バイクの個性があまり活かせなかったから、次はもうちょっとMTBよりのオールロードバイクを考えるよ。今はグラベルクラスもあるみたいだしね。こんな風に、グラベルレースはどんなバイク、装備で走るかを考えるのも楽しみの一つ。野辺山グラベルチャレンジはまだ走ったことがないけれど、面白そうだね。いつか走る機会があれば良いなと思っているよ。
日本のグラベルはアメリカのグラベルと比べると、少しテクニカルかもしれない。今回の房総ライドもそうだったけれど、どちらかといえば幅員の狭いガレたグラベルが多い印象。アメリカのグラベルは比較的スムースだし、クルマが余裕で走れる幅員のグラベルも少なくない。もちろんかなりガレたグラベルやシングルトラック、テクニカルなパートもあるけれど、そこがメインではない感じなんだ。オールロードバイクやグラベルバイクなら、ロードバイク感覚の延長線上で走れる道もたくさんある。だから、より多くのサイクリストがグラベルに移行しやすいのかもしれないね。
と、いろいろ話したけれど、なんと言っても、グラベルライドは楽しい! それがグラベルシーンを盛り上げている理由だと思う」。
何よりも、ストーリーが大事
ーー「バイシクルクォータリー」誌は創刊20年を迎えたとのことですが、自転車雑誌の編集をする上で大切にしていることは何でしょうか。
JH 「なによりもまず、ストーリーが大事なんだ。読者を引き込み、そのライドを自分が走っているかのように感じるようなストーリーを語ることが雑誌の役割だと思っている。そのうえで、徹底的な機材テストの記事が読めることもBQの特徴になっているのではないかな。
バイクをテストするときは走行レポートを重視しているよ。1台のバイクをテストするために最低でも300kmは走る。夜通し走るようなビッグライドに出かけることもあるし、新たなルートの開拓に出掛けることもある。ルートは毎回、テストするバイクのポテンシャルを見極めながら決めるんだ。バイクの特性にあった、それでいてちょっと攻めたルートを走ってみて初めて見えてくるバイクの個性もあるからね。そうしたバイクのテストのリポートにはドラマがあるから、読み物としても面白いんだ。
面白いことに、BQはアメリカで唯一、グロサリーストア(食料品店)で販売している自転車雑誌なんだ。しかも結構売上がいいんだよ。オーガニックフードの隣に自転車雑誌があるなんて素敵だろう?(笑) おそらくは健康志向の人たちに自転車の引き合いがあるということなのだろうが、ストーリーとして読ませる記事があるからこそ、彼らに手に取ってもらえているんだろう」。
BQ誌や書籍を刊行していくモチベーション、その情熱はどこにあるのでしょうか?
JH 「とにかく自転車に乗ることが好きで、その喜びを分かち合いたいということ。だから、『とにかく、乗ろう』という言葉に尽きるね。自転車に乗るときの楽しさ。情熱はそこから生まれてくるんだ」。
 尾根道のグラベルを行くと荒涼とした平原に出た photo:Makoto AYANO
尾根道のグラベルを行くと荒涼とした平原に出た photo:Makoto AYANO〜 エピローグ 〜
「オールロードバイク・レボリューション」は、自転車初心者向けの本ではないと思う。これは、自転車に乗る楽しみを覚えながら、さらにその喜びを深めたい人、既存の自転車メディアの紋切り型の発信に食傷気味な人、あるいは自転車の魅力を自由であることと考えられる人のための本ではないか。そして一面では、そうした人は自転車乗りとして成熟していると言えるかもしれない。
「ホイールのエアロダイナミクスよりもライディングフォームを正す方が空力は良く速く走れる」と著書の中で諭すように、ちょっとした下り坂をヤンさんはコンパクトなフォームで走っていく。共に走り、語った一日を終えたいま改めて本を開くと、まさに彼の口調がそこには再現されているのだった。断定的ではあるけれど、そこかしこにチャーミングな言い回し。彼の20年に及ぶ編集人としての集大成と、サイクリストとしての成熟がこの本に結実している。(小俣雄風太)
ヤン・ハイネ|Jan Heine プロフィール
アメリカ・ワシントン州シアトルに本拠を置く、自転車タイヤ/パーツのブランド『René HERSE』(ルネ・エルス)を主宰。自転車雑誌『Bicycle Quarterly』編集長。大学在学中に自転車レースを始め、大学院博士課程修了のころにはツール・ド・フランスを目指すプロ選手と伍するライダーとなるが、興味は長距離アドベンチャーツーリングへ。2007年「パリ~ブレスト~パリ1200㎞」において北米からの参加者中、最速を記録(49時間59分)。2016年には、自社で開発した53mm×26インチ幅の超軽量ロードタイヤ(1本418g)を履いた、FIREFLY(※)で王滝100kmに参戦(6時間27分)。2021 年には「OREGON OUTBACK」(585 ㎞・獲得標高4,382 m、26時間13分)FKT。2022年「Unbound XL」(530km・獲得標高4713 m、25時間24分)、「Arkansas High Country Race」South Roop(784㎞・獲得標高9973 m、46時間59分)FKT。1990年代初頭から、カスケード山脈のグラベル(砂利道)ルートを踏査し、科学的知見とサイクリストの経験を基にタイヤとパーツを20年にわたり開発してきた。
※ FIREFLY(アメリカ東海岸のチタンを得意とするフレームビルダー。53mm幅のタイヤを使ったロードレーサーに近いジオメトリのバイクは、彼らにとっても初めての試みでチャレンジであった)
Bicycle Quarterly(年4回発行)
https://www.bikequarterly.com
Rene Herse Cycles
https://www.renehersecycles.com
text:Yufta Omata
photo:Makoto AYANO,Yufta Omata,Naoshige Yoshimura
Amazon.co.jp


![[新版] ジャスト・ライド──ラディカルで実践的な自転車入門 (ele-king books) [新版] ジャスト・ライド──ラディカルで実践的な自転車入門 (ele-king books)](https://m.media-amazon.com/images/I/41mY6lz587L._SL160_.jpg)





