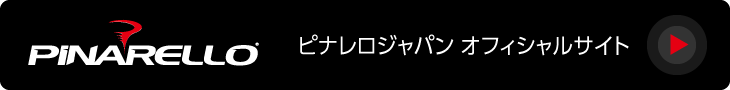アメリカ、そしてヨーロッパで急速に進化を遂げる“レーシンググラベル”の世界。その最前線にピナレロが送り出したのは、DOGMA Fの名を継ぐDOGMA GRと、実直な走りのGREVIL F。プロセッコの葡萄畑が広がる丘陵地帯を舞台に行われたイタリア試乗会で、この2台の実力と「速さへの哲学」を体感した。
そんなロードレースカルチャーと、プロセッコの芳醇な空気が入り混じる土地をグラベルバイクで走るという贅沢──それが今回のテストライドだ。

アルプス山脈の麓にあるイタリア北部の街・コネリアーノはプロセッコ用のワインが栽培される街 photo:So Isobe

無数に用意された新型グラベルバイクたち photo:Pinarello 
ライドを引っ張るのはラモン・シンケルダム。2023年までプロロード選手として走り、今年のアンバウンドでは6位に入った photo:So Isobe
コースは、まさにローカルの案内無しではたどり着けないルートの連続だった。ホテルを出発したと思ったらすぐ小道(というか、ただの藪)に分け入り、怒られるんじゃないかと不安になる葡萄畑のトラクター道を突き進む。MTB向けと思えるほどの急勾配で荒れた場所から、気持ちよく飛ばせる整備された白い砂利道、そして舗装路へ。めまぐるしく表情を変える道を繋ぐ過程で乗り味を確かめる。
最初にDOGMA GR、続いてGREVIL Fと乗り換えた。試乗をリードしたのは、DOGMA GRのプロトタイプを駆り、アンバウンド・グラベルで6位に入ったラモン・シンケルダムだ。1年半前までプロトンでスプリンターの最終発射台として名を馳せた脚は健在で、重厚なペダリングでジャーナリストの列を(軽々と)引っ張り続けた。

塊のような剛性感。あらゆる挙動が早く、どこからでもスピードに繋がる photo:Pinarello
DOGMA GRに試乗して真っ先に思ったことは、「DOGMAは、グラベルになってもピュアレーサーだ」ということだ。
車体全体から漲るあふれんばかりの剛性感は、これまで何回もイタリアの発表試乗会で感じてきたDOGMAそのものだ。ヘッドからダウンチューブ、ボトムブラケットにかけての剛性はグラベルモデルと思わせないレベルで高く、ロードのエンデュランスモデルであるDOGMA Xはその硬さをしなやかさで上手く包み込んでいるが、グラベルレースでの勝利をひたすらに追い求めて生まれたDOGMA GRは獰猛さを一切隠そうとなんかしていない。
ボトムブラケット周辺の剛性も極めて高く、硬く、速く走らせるのであれば乗り手にも一定以上のパワーと綺麗に真円をなぞるペダリングを要求してくる。これもDOGMA Fと全く同じ性格だ。
でも、それだけに、DOGMA GRの加速力は目覚ましいものがある。取り付けられたタイヤが40Cだと思わせないほどダッシュが軽く、大きなパワーを入力するや否や車体はバチン!と前に弾け飛ぶ。下ハンドルを握り、思い切りペダルに体重を乗せるようにスプリントした時の加速っぷりは素晴らしいことこの上ない。

プロセッコの畑の中を駆け上がる。極上のグラベルルートが多数ある場所だった photo:Pinarello
加速、巡行、減速、コーナリング、出口での再加速。一連の動作に全く淀みはなく、スパルタン。開発ライダーを務めたコナー・スウィフト(イネオス・グレナディアーズ)が一番に求めたという「即座に応える反応性」が見事に実現されているし、ピナレロのバイクであらゆるタイトルを手にしてきたトム・ピドコックが「これはDOGMA F。ただ太いタイヤを履けるようになったDOGMA Fだ」と言ったことにも納得できる。
フレームの乗り心地は、正直言ってあまり良くない。と言うよりも、衝撃吸収はタイヤに任せている、と汲み取るのが正しいだろう。DOGMA GRはピナレロが言う「ファストグラベル(グラベル世界選手権に代表される整った未舗装路)」でのレースに絞ったモデルだから、乗り心地ではなくレスポンスが優先されているのは当然のことだ。

20%近い簡易舗装の激坂区間。脚と元気が満タンならDOGMA GRの硬さは恐ろしいまでの武器になる photo:Pinarello
ヘッドチューブが低いジオメトリーもかなり戦闘的で、下ハンドルを握れば相当にポジションは低くなる(新ジオメトリーのおかげで辛さは感じなかったが)。同時開発されたハンドルもDOGMA F同様に硬く「手や上半身への衝撃を和らげる」意図は感じ取れない。しかし、快適性を優先してタイヤの空気圧を抜きすぎればせっかくの走りをスポイルすることに繋がってしまうので、行くてに大きなギャップがあれば乗り手がそれを見つけ、予測して、身体の動きで衝撃をいなすのがDOGMA GRの乗り方として正しいと思う。

筆者に用意されたGREVIL FはT900カーボンのF7完成車(カラーは市販されないプロトタイプ) photo:Pinarello
DOGMA GRから小休止を経てGREVIL F(T900カーボンを使ったGREVIL F7完成車)に乗り換えると、この2台は全く異なる設計思想から生まれたものだ、と気付かされるのだった。
先述したようにDOGMA GRはどこまでも硬く速いピュアレーサーだが、GREVIL Fはもっとしなやかで、流れるように速度を乗せていく。「快適だけど走りが重い」というありがちなマイナス部分は無く、あらゆる状況でスムーズ。見た目に反して軽いオリジナルホイールとの相乗効果もあって、淀みなく高速域まで伸びる。
ダッシュに対して素早く反応するのはDOGMA GRだが、5時間以上のレースを踏まえて設計されたGREVIL Fは、ごく僅かに「タメ」を作ってからグッと加速する。どちらも速い「ピナレロのレースバイク」であることには変わらないのだが、ペダリングに対する許容範囲も広いから踏み負けてしまう雰囲気も薄い。流して走っている時や、前のライダーを追いかけているとき、脚がいっぱいで心が折れそうになっているとき、そんな苦しいときに寄り添ってくれるのはGREVIL Fだ。

GREVILはDOGMAに比べて「踏みしろ」量が多い。苦しい時や流している時でも綺麗にスピードが乗る photo:Pinarello

小休止...。メディア同士でバイクの印象を共有する photo:Pinarello 
世界文化遺産に登録されたプロセッコ栽培丘陵群 photo:Pinarello
ハンドリングの切れ込みは依然として鋭く、50mmリムに45mmタイヤをつけているのに左右の細かい切り返しも不得意じゃない。路面からの突き上げもDOGMA GRに乗った後だと相当マイルドに感じるから、あえて座ったまま荒れたグラベルに突っ込んでみても、シートポストとリアバックが積極的に衝撃を和らげていることが分かった。ジオメトリーもDOGMA GRほど攻めてはいないので、おそらく誰が乗っても扱いにくいバイクだ、と思うことはないだろう。

熱を帯びるグラベルレーシング界にピナレロが放ったDOGMA GR
DOGMA GRとGREVIL F。2台の走りのアプローチは異なるものの、実際に乗ってるみるとどちらも等しく「速さ」を求めたバイクだ。DOGMA GRは体力もスキルもあるユーザー向けだが、爆発的なまでの走りを味わうための相棒として選ぶのも十分にあり(ロードモデルのDOGMAと同じように)だと思う。
DOGMA GRに関しては、正直、こんなに過激なバイクを誰が乗りこなせるのだろうか、という疑問が頭をよぎった。でもグラベルテストの翌日、近日発表予定のロードモデルのテストライドの際、45km/hほどで走っている我々をローカルのグラベルチームの選手が(グラベルバイクとタイヤで。しかも一人で)あっさり追い抜いていったのだ。欧米には日本人の我々の想像を遥かに超えるレベルで「グラベルレース」が浸透し、本気の競技として成熟しつつある。そういう場面で求められる最前線にピナレロが放ったバイクこそ、このDOGMA GRだ。

乗りやすさとスピード、積載力までを兼ね備えたGREVIL F photo:Pinarello
一方で、誰にでも乗りこなせるフレンドリーさがGREVIL Fの魅力だ。今回は上位グレードを試乗したが、おそらくピナレロの定石からすれば、カーボンが異なるミドル〜エントリーグレードはもっとマイルドな乗り味になっているはず。未舗装路を含めて長距離を旅するにも良いだろうし、DOGMA GRには無い積載力を活かしてバイクパッキングに使うのも十分あり。舗装路メインであっても、40mm以上のスリックタイヤを履かせた最新スタイルで週末ライドの相棒にするのも悪くないと思う。
日本のグラベル人口こそまだ小さいが、8月に宮城県加美町で開催される「グラベルクラシックやくらい」は、2026年のUCIグラベルワールドシリーズ招致を見据えた国内初の本格レースとして準備されているなど、潮目は少しずつ変わり始めたように思う。どちらのバイクも、これから層が厚くなるであろう、成績を狙うコアなグラベルファンにとっては魅力的な選択肢となるはずだ。
ジロの激坂を越え、プロセッコの葡萄畑を走る
ピナレロの新たなグラベルマシン「DOGMA GR」と「GREVIL F」の発表会場は、イタリア北部、ヴェネト州のコネリアーノ──静けさと歴史が折り重なる、プロセッコのブドウ畑に囲まれた丘陵地帯。何度もジロ・デ・イタリアに登場する激坂「ムーロ・ディ・カ・デル・ポッジオ」の頂上にあるホテルのエントランスにはピンク色の写真やサインボードが飾られ、“ピンクの祭典”の記憶を雄弁に物語っていた。そんなロードレースカルチャーと、プロセッコの芳醇な空気が入り混じる土地をグラベルバイクで走るという贅沢──それが今回のテストライドだ。



コースは、まさにローカルの案内無しではたどり着けないルートの連続だった。ホテルを出発したと思ったらすぐ小道(というか、ただの藪)に分け入り、怒られるんじゃないかと不安になる葡萄畑のトラクター道を突き進む。MTB向けと思えるほどの急勾配で荒れた場所から、気持ちよく飛ばせる整備された白い砂利道、そして舗装路へ。めまぐるしく表情を変える道を繋ぐ過程で乗り味を確かめる。
最初にDOGMA GR、続いてGREVIL Fと乗り換えた。試乗をリードしたのは、DOGMA GRのプロトタイプを駆り、アンバウンド・グラベルで6位に入ったラモン・シンケルダムだ。1年半前までプロトンでスプリンターの最終発射台として名を馳せた脚は健在で、重厚なペダリングでジャーナリストの列を(軽々と)引っ張り続けた。
獰猛な剛性、驚異のダッシュ。DOGMA GRは速さの塊

DOGMA GRに試乗して真っ先に思ったことは、「DOGMAは、グラベルになってもピュアレーサーだ」ということだ。
車体全体から漲るあふれんばかりの剛性感は、これまで何回もイタリアの発表試乗会で感じてきたDOGMAそのものだ。ヘッドからダウンチューブ、ボトムブラケットにかけての剛性はグラベルモデルと思わせないレベルで高く、ロードのエンデュランスモデルであるDOGMA Xはその硬さをしなやかさで上手く包み込んでいるが、グラベルレースでの勝利をひたすらに追い求めて生まれたDOGMA GRは獰猛さを一切隠そうとなんかしていない。
ボトムブラケット周辺の剛性も極めて高く、硬く、速く走らせるのであれば乗り手にも一定以上のパワーと綺麗に真円をなぞるペダリングを要求してくる。これもDOGMA Fと全く同じ性格だ。
でも、それだけに、DOGMA GRの加速力は目覚ましいものがある。取り付けられたタイヤが40Cだと思わせないほどダッシュが軽く、大きなパワーを入力するや否や車体はバチン!と前に弾け飛ぶ。下ハンドルを握り、思い切りペダルに体重を乗せるようにスプリントした時の加速っぷりは素晴らしいことこの上ない。

加速、巡行、減速、コーナリング、出口での再加速。一連の動作に全く淀みはなく、スパルタン。開発ライダーを務めたコナー・スウィフト(イネオス・グレナディアーズ)が一番に求めたという「即座に応える反応性」が見事に実現されているし、ピナレロのバイクであらゆるタイトルを手にしてきたトム・ピドコックが「これはDOGMA F。ただ太いタイヤを履けるようになったDOGMA Fだ」と言ったことにも納得できる。
フレームの乗り心地は、正直言ってあまり良くない。と言うよりも、衝撃吸収はタイヤに任せている、と汲み取るのが正しいだろう。DOGMA GRはピナレロが言う「ファストグラベル(グラベル世界選手権に代表される整った未舗装路)」でのレースに絞ったモデルだから、乗り心地ではなくレスポンスが優先されているのは当然のことだ。

ヘッドチューブが低いジオメトリーもかなり戦闘的で、下ハンドルを握れば相当にポジションは低くなる(新ジオメトリーのおかげで辛さは感じなかったが)。同時開発されたハンドルもDOGMA F同様に硬く「手や上半身への衝撃を和らげる」意図は感じ取れない。しかし、快適性を優先してタイヤの空気圧を抜きすぎればせっかくの走りをスポイルすることに繋がってしまうので、行くてに大きなギャップがあれば乗り手がそれを見つけ、予測して、身体の動きで衝撃をいなすのがDOGMA GRの乗り方として正しいと思う。
速さも快適さも。GREVIL Fは誰でも扱えるレースバイク

DOGMA GRから小休止を経てGREVIL F(T900カーボンを使ったGREVIL F7完成車)に乗り換えると、この2台は全く異なる設計思想から生まれたものだ、と気付かされるのだった。
先述したようにDOGMA GRはどこまでも硬く速いピュアレーサーだが、GREVIL Fはもっとしなやかで、流れるように速度を乗せていく。「快適だけど走りが重い」というありがちなマイナス部分は無く、あらゆる状況でスムーズ。見た目に反して軽いオリジナルホイールとの相乗効果もあって、淀みなく高速域まで伸びる。
ダッシュに対して素早く反応するのはDOGMA GRだが、5時間以上のレースを踏まえて設計されたGREVIL Fは、ごく僅かに「タメ」を作ってからグッと加速する。どちらも速い「ピナレロのレースバイク」であることには変わらないのだが、ペダリングに対する許容範囲も広いから踏み負けてしまう雰囲気も薄い。流して走っている時や、前のライダーを追いかけているとき、脚がいっぱいで心が折れそうになっているとき、そんな苦しいときに寄り添ってくれるのはGREVIL Fだ。



ハンドリングの切れ込みは依然として鋭く、50mmリムに45mmタイヤをつけているのに左右の細かい切り返しも不得意じゃない。路面からの突き上げもDOGMA GRに乗った後だと相当マイルドに感じるから、あえて座ったまま荒れたグラベルに突っ込んでみても、シートポストとリアバックが積極的に衝撃を和らげていることが分かった。ジオメトリーもDOGMA GRほど攻めてはいないので、おそらく誰が乗っても扱いにくいバイクだ、と思うことはないだろう。
世界はグラベルレース活況 日本の夜明けなるか?

DOGMA GRとGREVIL F。2台の走りのアプローチは異なるものの、実際に乗ってるみるとどちらも等しく「速さ」を求めたバイクだ。DOGMA GRは体力もスキルもあるユーザー向けだが、爆発的なまでの走りを味わうための相棒として選ぶのも十分にあり(ロードモデルのDOGMAと同じように)だと思う。
DOGMA GRに関しては、正直、こんなに過激なバイクを誰が乗りこなせるのだろうか、という疑問が頭をよぎった。でもグラベルテストの翌日、近日発表予定のロードモデルのテストライドの際、45km/hほどで走っている我々をローカルのグラベルチームの選手が(グラベルバイクとタイヤで。しかも一人で)あっさり追い抜いていったのだ。欧米には日本人の我々の想像を遥かに超えるレベルで「グラベルレース」が浸透し、本気の競技として成熟しつつある。そういう場面で求められる最前線にピナレロが放ったバイクこそ、このDOGMA GRだ。

一方で、誰にでも乗りこなせるフレンドリーさがGREVIL Fの魅力だ。今回は上位グレードを試乗したが、おそらくピナレロの定石からすれば、カーボンが異なるミドル〜エントリーグレードはもっとマイルドな乗り味になっているはず。未舗装路を含めて長距離を旅するにも良いだろうし、DOGMA GRには無い積載力を活かしてバイクパッキングに使うのも十分あり。舗装路メインであっても、40mm以上のスリックタイヤを履かせた最新スタイルで週末ライドの相棒にするのも悪くないと思う。
日本のグラベル人口こそまだ小さいが、8月に宮城県加美町で開催される「グラベルクラシックやくらい」は、2026年のUCIグラベルワールドシリーズ招致を見据えた国内初の本格レースとして準備されているなど、潮目は少しずつ変わり始めたように思う。どちらのバイクも、これから層が厚くなるであろう、成績を狙うコアなグラベルファンにとっては魅力的な選択肢となるはずだ。
提供:カワシマサイクルサプライ
text:So Isobe
text:So Isobe